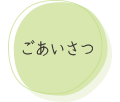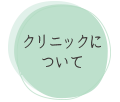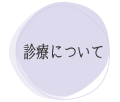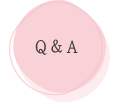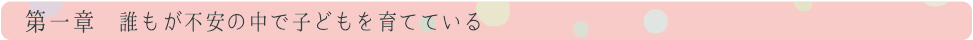
A1. 未熟児で生まれた子
A2. 難産で生まれた子
A3. 手や顔に奇形を持つ子
A4. 心臓〔内臓〕に先天的な病気がある子
A5. ひきつけがある子
A6. なかなか歩いてくれない子
歩行開始の遅れは、ご両親が最も心配されることのひとつですね。手助けなしには好きなところへも行けなかった子どもが、思いのままにあちこちへ行けるようになるのですから、まさに歩き始めることは一人立ちの第一歩と感じられるでしょう。それだけに歩行開始の遅れが一人立ちの遅れのように思われて、不安になるのではないでしょうか。
子どもの発達にはさまざまな側面がありますが、次の四つに分けて考えるのがわかりやすいとされます。第一に、イナイイナイバーに反応して笑ったり、別れぎわにバイバイをしたりする対人・社会的発達。第二に、自分の名前に反応したり、喃語を発する言語的発達。第三に、ガラガラを振ったり、小さなゴミを見つけて拾い上げる微細な運動発達。そして、首が座ったり、つかまり立ちができるようになる粗大な(おおまかな)運動発達の四つです。歩行開始はこの粗大な運動発達の一段階です。
子どもの発達はこれらに代表されるようなさまざまな項目の発達の複合体ですが、どの子どももすべての項目が等しく発達していくのではなく、得意なところと苦手なところを持ちながら発達していきます。一つ一つの発達の個人差も含めると、たとえ兄弟であっても、みんな別々の発達の仕方をするものなのです。歩行開始の個人差は、10ヵ月から1歳半までと、かなりの幅を持っています。早く歩き始めた子どもが発達が早いというわけではありません。逆に、1歳半までに歩ければ、おおまかにいって運動発達の面では正常であると言ってよいでしょう。
1歳半を越えてもなお歩行開始がない場合には、専門的な診察と評価を受ける必要があります。保健所の発達相談や、小児の神経の専門外来を持っている病院などを受診して相談なさってください。その時点ではまだはっきりせず、定期的にみていくように言われるかもしれませんが、遅くとも2歳で歩行が得られない場合は精密検査を受けると同時に、やはり訓練や療育といった専門家の指導が受けられる場をもつべきだと思います。
子どもが発達に問題を持った場合、よく起こることは、苦手な面を使わずに成長しようとすることです。歩くのが苦手な子どもの場合は、移動することをあきらめて、自分が動ける狭い範囲の世界で成長してしまうのです。同世代の子どもが公園の砂場でどろんこになって遊んでいるときに、家の中で過ごしていては、残りの3つの項目の発達に影響が出てしまいます。そばにいる大人がまずやってあげたいことは、どんどん外に連れ出して経験の差をつくらないようにすることです。歩けることは、発達の目標ではなく、発達するための手段なのだという認識をもって、お子さんの発達の手助けをしてあげてください。
A7. 言葉をなかなかしゃべってくれない子
発達についての相談で最も多いのが言葉の遅れに関するもので、その95%は男の子です。かなり個人差があるため、そのことだけを医師などに相談しても、「もう少し様子を見ましょう」と言われることが多いようです。確かに様子を見ているうちに言葉が出てくる例も多いのですが、他に原因がある場合、その種類によっては、きちんとしたアプローチをしないと、言葉が身につかない場合もあります。
大まかにいうと、1歳で「ママ」などの単語が、2歳で「目、鼻」等の指差しや「ママいない」などの二語文が言えるようになります。また、言葉はコミュニケーションの手段ですから、同年代の子どもと対等に渡り合えるかどうかが、言葉の数よりも重要な目安になります。
そうした点で見ても、お子さんの言葉が遅れていると思われるならば、まず近くの保健所に相談されるとよいでしょう。保健所は、子どもの健康・発達全般に取り組んでいて、発達を定期的に見る専門医の外来もありますから、利用してみてはいかがでしょうか。遅れとははっきり断定できない場合でも、発達を促すためのグループを紹介してくれることもあります。発達について専門に取り組んでいる地域の療育相談機関に直接相談を持ちかける方法もあります。中・大規模の病院で小児科がある場合には、窓口でどの医師に相談したらよいか尋ねてみるのもよいでしょう。医師の専門をよく知っている受付の事務員や看護婦が、よい医師を教えてくれることでしょうし、専門医が定期的に外来を行っている場合もあるかもしれません。
言葉の遅れは、気になりだした時が相談の時期です。「もう少し、様子を見ましょう」と言われた場合でも、定期的に見てくれる場所を確保して、お子さんの問題点を一日でも早く発見することが、発達を促すのに最も大切なことだと思います。
A8. なかなか視線が合わない子
しかし、自閉的かどうかはかなり主観的な概念なので、自閉症の診断には慎重さが必要です。最近の診断規準では、16項目にも及ぶ行動形態があげられて、これらのうちいくつかを満たしている場合に診断されます。これは、児童精神科医という子どもの心の専門医によって行われます。
多くのご両親は、知的発達がどうなるかについて心配されます。言葉は人に何かを伝える道具ですから、自閉症の場合、適切な言葉づかいをするうえで障害が生じます。知的発達は、学校教育をはじめ人との関わりの中で育つ側面が大きいので、自閉症の子どもの場合、知的発達は遅れる場合が多いようです。しかし、文字や数字に対する興味や、場面を認識する能力がすぐれている場合もあり、小さな環境の変化を捕える能力の鋭さに驚かされることもしばしばです。
自閉症はこのようにかなり特徴のある性格を持っています。もし、お子さんがこうした性格を持っているなと感じたなら、早めに児童精神科の門をたたいてください。早期診断を得れば、早期から適切な教育が受けられるからです。
自閉症は医学的にはかなり古くから知られている疾患で、従来から多くの教育方法や訓練方法が試みられています。決定的な方法が確立しているとは言えませんが、いくつかのアプーチをお子さんに経験させる価値はあると思います。その際、お子さんがその訓練法に接したときの様子を見極めてください。もし、ご両親の目から見て、お子さんに合っていない、お子さんが適応していないと判断したなら、別の方法を試してみる勇気を持ちましょう。わが子の育て方なのですから、ご両親が納得する方法を見つけることが大切です。
そうした性格をすぐに病気と結びつけるのは短絡的ですが、その程度が著しく、本人が危険にさらされたり、まわりの者が振り回されて極端に負担がかかる場合、「注意欠陥障害」、「多動」と呼ばれることがあります。この病気の診断は一般の医師にも難しく、子どもの心の病を専門とする児童精神科医の診察が必要になります。
治療には、薬物療法も行われることがありますが、それは落ちつきのなさがある程度を越えた場合に限ります。基本的には、まわりにいる大人が本人の性格を伸ばせる環境を作ってあげることが大切だとされています。落ちつきがない子は、特に小学校に入ってからの集団生活の場で大人から問題視されることが多く、本人がそのことを気にしてしまうと成長にゆがみを生じてしまいます。幼稚園や学校の担任とよく話し合って、子どもにあった環境づくりをこころがけてください。
もし問題が生じるようなら、早めに児童精神科医の診察を受けましょう。保健所や大学病院などのほか、地域の療育相談機関で尋ねてみてください。
A10. 病院に行くと検査ばかり
ご両親がそのように思われるのは、きっと病院で十分納得のいく説明を受けていないからでしょうね。外来を担当する医師の一人として、申し訳なく思います。最近ではインフォームド・コンセントといって、自分、あるいは子どもが受ける医療について、納得いく十分な説明を受ける権利があるという考えかたが一般的になっています。つまり専門医には、いつでも十分な説明をしなければならない義務があるわけです。
お聞きになりたいことは、ざっくばらんに尋ねてみてください。それが主治医と仲良くなれるチャンスにもなります。毎回でなくても、年に何度かはお父さんも一緒に主治医のもとを訪れ、お父さんが直接質問されたり、医師と話し合われることもお勧めします。
障害をのこす病気は、原因が特定できない場合が多く、診断が確定するまで、たくさんの検査が続くこともあります。お子さんの受ける検査がどのような目的で行われるのかを正しく知っておくためにも、きちんと説明を受けることが大切になってきます。
一度診断がついた場合には、その病気によって注意しなくてはならない合併症や、病気の程度の変化を定期的に確認することが大切です。そのために、年に一、二回の定期検査が必要になります。特に、てんかんの診断がついている場合には、飲んでいる薬による副作用のチェックを、少なくとも半年に一度受けなければなりません。また、年齢によって変化が起こる場合があるので、脳波の検査も最低一年に一度は受けるのが望ましいでしょう。
医学は、お子さんの抱える問題の一部しか解決できないかも知れませんが、お子さんの体に直接関わる大事な分野です。どうぞ十分に納得をして、医師と対等で良好な関係を築いてください。どうしても医師との信頼関係が築けそうにない場合は、ためらわず他の医師を探すことをお勧めします。お子さんが一生医療とつきあう必要があるのなら、そのためにご両親が安心してまかせられる主治医を探す努力は大切だと思います。
A11. 共働きは無理?
いまお子さんが何を必要としているかによるでしょう。お子さんの状態によっては、むしろ両親から離れて、他のお子さんたちの集団で過ごしたほうがよい場合もあります。また、一方で学校に入学すれば必ず両親と離れて通学することになります。このため、就学までに解決しておいた方がよいことがあることも事実です。
一般に心身の最も盛んな成長期である乳幼児期には母子間の健全な交流が必要とされています。過保護になることを慎まなければなりませんが、両親の情緒的な関わりが大変重要です。
お子さんがいま何を必要としているかは後に述べる専門機関で相談してみるとよいでしょう。専門機関での指導は、通常週に1〜3回程度です。共働きをつづける場合は、保育園の通園などと組み合わせる必要があります。また、おじいちゃんやおばあちゃん、ホームヘルパーや家庭指導員、ボランティア等の助けを必要とするかも知れません。自分たちだけで悩まずにみじかな人たちにも相談してみることも必要でしょう。
仕事をする事の意味は、その人にとって自分自身の存在を実現し、生きている証を感じることだと思います。仕事をつづけている方が精神的に安定して子どもに接することができるならば、お子さんのために働くことも必要かもしれません。
A12. 他の兄弟の面倒が十分に見られない
障害を持つ子どもの療育には、多大な労力や時間が費やされ、経済的な負担も大きくかかります。親は心労、過労が続き、病気になる場合さえあります。
家族の一員である兄弟も大きな影響を受けます。障害児の誕生でショックを受けた両親が、悲しみや怒り、不安を抜け出して、現実を受け入れて希望を持ち、広い視野に立って考えられるようになるまでには、しばらく時間がかかります。両親が悲しみの段階にあると、家族の機能がうまく働かないので、兄弟たちは子どもとしての依存や欲求を十分受けとめてもらえなくなり、ノイローゼになったり、障害をもつ兄弟に心の中で強い憎しみや恨みを抱くようになる場合もあるのです。一般に兄や姉には、障害児の誕生によって両親からの愛情が突然奪われて欲求不満を起こす例が見られますが、弟や妹は、自分の生まれる前からあった状態により容易に適応できるといわれます。
悲しみの過程を経過し、再起の段階に達すると、両親は障害を持つ子どもだけでなく、他の子どもにも必要な世話を十分に与えることができるようになります。兄弟が親の愛情を受け、充足した幼児期を経て、納得できる楽しい学校生活を送り、思春期を迎えると、親の生き方を理解しやがては、自分なりに障害を持つ兄弟に役立つことをしようと考え始めることでしょう。
母親の障害児に対する感情や態度は、子どもたちの成長発達に大きな役割を占めています。障害児はふつうの子どもより、自分から母親に働きかけることが少ないので、母親がその子の反応を敏感に読み取り、よほど忍耐強く工夫して育てないとよい母子関係が育ちません。 両親自身が、障害をもつ子どもに自分たちなりに精一杯のことがしてやれている、という納得と自信を持てるようになることで、子どもは親に質問し、親の答えによって安心していろいろの障害を乗り越えていけるのです。親自身が不安なために子どもの質問を避けたり、時期尚早に障害について理屈で説明したり、兄弟としての責任を説いたりしすぎると、子どもは違和感や恐れを抱き、障害を持つ子どもの存在を負担に感じてしまいます。
日常生活のあらゆる場面で、親は子どもに影響を与え、子どもとともに社会から影響を受けています。かりに障害児と親や兄弟が家族としてまとまっていても、注意しないと家族ごと社会から離れてしまう恐れもあります。
兄弟が治療に参加することは、家族全体に大きな変化をもたらします。兄や姉が、たとえば一週間のキャンプに行き、そこで他の兄や姉に関わることは大きな意味を持ち、その結果兄弟たちが自分自身を変革していくという体験を身につけるでしょう。
障害児から逆に両親や兄弟が教えられるという例は多いのです。親やまわりの人が変わるのです。ある弟が障害児の兄の思い出を書いた本に次のようなことが述べられていました。母親が兄弟にむかって、「目が見えるということはありがたいことなのね」とか「おまえが国にいったら○○ちゃんが走り寄ってきて、抱きしめてくれるよ。そしておまえにいう最初の言葉は『ありがとう』なのよ」といった会話が、子どもの心に忘れられない印象を残したと言うのです。そしてその障害児の存在によって家族が祝福されていたと述べてありました。
A13. いのちが育まれるとき
5歳になるその子が発見されたのは、自宅のベビーベッドの中でした。体重は6キロ、身長も85センチと、外見はまるで赤ちゃんそのものでした。1歳半の時に交通事故で一時入院したのをきっかけに、母も父もその子の成長を期待しなくなり、それ以来成長を止めてしまったのです。「愛情遮断症候群」と呼ばれるこの疾患は、現代の日本でもまれならず報告されています。
体の発達と心の発達は別々のものと思われがちですが、実は互いに必要不可欠なのです。
生まれたばかりの赤ちゃんに、お母さんはいっしょうけんめいに語りかけます。赤ちゃんが笑えばお母さんは喜び、泣けばうろたえます。この一見単純な関係が、赤ちゃんの成長にとっては不可欠なのです。お母さんの喜びを引き出すために、赤ちゃんは同じ表情を繰り返し、ほほ笑むことを覚えます。遠くにいるお母さんを呼ぶためにもっとも有効な合図は、泣き声をあげてお母さんを不安にさせることだということにも気付きます。そんなふうにして、親との関係の中で赤ちゃんは自分の意志を伝える方法を覚えるのです。
ですから、親からの「すくすくと育って欲しい」という希望が伝わらずに放って置かれると、赤ちゃんは何を頼りにどう発達していったらよいのか判断することができずに、脳の成長を止めてしまいます。そして、心の成長が止まるだけでなく、成長ホルモンの分泌も抑えてしまい、体の成長も止まってしまうのです。これが愛情遮断症候群の病態とされています。
子どもの発達に、そばにいる大人の成長を喜ぶ気持ちがいかに大切かをこの疾患は教えてくれます。体や心の発達に問題を抱えた子どもには、ことに近くにいる大人達の成長への応援が必要なのですが、こうした場合、残念ながら、お子さんの発達を見つけ、お子さんとともに喜べる余裕がないご両親が多いのです。
医師に病名や障害を告げられた瞬間から、ご両親はご自分の気持ちを落ちつかせるために長い月日を費やさなくてはなりません。病気に対する憎しみや、成長に対する不安がつのるために、いつのまにか喜びを感じる余裕がなくなってしまうのでしょう。また、成長していることを確認する手段として、育児書や同年齢の子どもと比べてしまったりすると、いつまでも遅ればかりに目が向いてしまうのです。そうすると、確実に成長している別の側面に気付くこともできなくなってしまうのです。
「カー君」は特殊学級に通う小学校3年生の男の子です。その日、日直のカー君は黒板の前に立っていました。「今日は何月何日かな」という先生の声に答えようと、カー君はチョークを取って黒板に向かいました。横に一本書いて、その左端から下に一本書いて、チョークはその下端で止まりました。5秒、10秒、⋯⋯カー君は5の字を書こうとして、どちらに曲げればよいのか迷っていたのです。教室にいた十数人のクラスメートのうち、どう書けばよいのかわかっている数人はしきりに「右だよ、右」と、大声で応援していました。残りの子たちも思い思いに「あっちだ、こっちだ」と教えようとしていました。30秒、40秒、⋯⋯その教室にいた二人の教師と一人の実習生もずっと祈るような気持ちで見守っていました。50秒⋯⋯カー君はじっと黒板を見つめています。60秒、70秒、⋯⋯教室中が「カー君ガンバレ、カー君ガンバレ」の大合唱に包まれたその瞬間、カー君の手は右へ弧を描いたのでした。そして、教室の中は拍手の渦でいっぱいになりました。
ほんの数分のできごとでした。5の字をどう書くかという、ほんの些細な成長の瞬間でしたが、その場に居合わせた十数名のクラスメートと二人の教師と一人の実習生は、その小さな成長の瞬間を、祈るような気持ちを抱きながら、共有することができたのです。そして、カー君はその祈りのまん中にいました。きのうまで自信のなかった一つのことができてうれしかったのと同時に、たくさんの友だちと先生が自分のことを応援しているということを、体全体で感じることができたのです。
お子さんが1ヵ月前、3ヵ月前にできなかったことが、きょうできるようになったら、お母さん、お父さんはそれに気づくことができますか。気づいたとして、それを心から喜べますか。そして、ご自分が喜んでいることを、お子さんに伝えられますか。将来への不安が、小さな成長を見つけるじゃまをしてはいませんか。何かに対する怒りが、喜びをさえぎっていませんか。最後にお子さんを抱きしめて、喜びを伝えたのはいつですか。
お子さんの将来を見据えて、周到に準備を進めることは大切ですし、不安は簡単にぬぐえるものではありません。しかし、将来、お子さんは自分自身で人生を歩んでいかなければなりません。頭が柔らかな子どものうちに、心とからだに「こんな子になって欲しい、こんなことを大切にして生きていって欲しい」という親のメッセージをしっかりと伝えて、お子さんに生きる方向性とエネルギーを与えてあげなければなりません。なぜなら、いのちはそうやって育まれてゆくものだからです。
「のんき、こんき、げんき」という言葉があります。お子さんを育てていくお母さん、お父さんが、この先の長い道程を乗り切るためには、まず体が健康でなくてはなりません。子どもの小さな発達を喜べる余裕が生まれるくらい、心の健康も同時に保たなくてはなりません。根気強さも大切です。そして、その思いを持続させるためには、支えてくれる仲間が必要です。配偶者あるいは他の家族、友人や学校の教師、誰でもよいですから、何でも打ち明けられる人を近くに作ってください。そして、気持ちを長持ちさせるためには、「のんき」でいることも忘れないでください。ときには気持ちを解放して自分だけの時間を作ったり、好きなことに没頭する時間を持つことで、心とからだがリフレッシュされ、余裕が生まれるのです。そうして、お子さんを包み込むあたたかさが生まれた時、お子さんも心底安心してあなたのそばにいられるようになり、心も体ものびのびと成長していけるようになるのです。
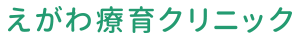
〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2256ジュンヌフイヤージュ1F
Tel:044-712-4056 Fax:044-712-4138